第十七章
 ゾーネンニーデルン ロディウムの隠れ里 ラインハルトにあてがわれた部屋は小振りながらも気配りの行き届いた居心地よさそうな部屋だった。 一人になると急に疲れが出て、ラインハルトはきれいに整えられたベッドの上に無造作に身を投げだした。 ここ数日立て続けに様々な重大事を告げられ、頭が混乱気味だ。 そのせいか先ほどからずっと鈍い頭痛が続いていた。 どの一つをとってみても自分の手には余るようなことがこうも重なると、ラインハルトとしてはどう手を着けていいか分からず、いっそのこと全て投げ出してしまおうかという衝動に駆られてしまいそうになる。 「ああ、もう、一体何だって言うのだ!」 そう声に出して見ても何も解決するはずもなく、ラインハルトの苦渋は深まるばかり、疲れなど一向にとれそうにない。 フィリップ卿から聞かされたあまりにも衝撃的な先祖にまつわる話――― どうにも信じがたい話だが、あの異空間で耳にした兄の言葉を思い起こすと、全くの作り話と頭から否定することはできない気がした。 少なくとも兄が何事かを深く思い悩み、ヴィクトールに打ち明けたことが、今回の騒動の発端であることは間違いないように思える。 それは王族である自分にすら秘された事柄―――王となる者だけに代々口伝により伝えられてきた事柄なのだろう。 ラインハルトは今更ながら兄が抱える苦悩の一端すら担えなかった自分に歯噛みしたいほどの情けなさを感じた。 自分はヴィクトールほどには兄に信頼されていなかったということだろうか・・・ そうではない、兄は自分に余計な心配をさせまいと思ったのだ。代々伝わる血の汚点―――そんな重荷を自分には抱え込ませたくないという配慮だったのだろう。そうは分かっていてもやはり寂しいものがあった。 自分はどんな重荷であろうとも兄とともに担うのであれば、少しも厭いはしないのに・・・ そしてまたつい今しがた知らされたルドルフの秘密――― 彼女が女でありながら男として育てられた理由は分かった。 ルドルフの母はお産で命を落としていると聞いた。 父のステファン王子は生まれたばかりの王女をどうしても手放すことができなかったのだろう。その面ざしが母に生き写しであればなおさら。 だから表向きは第二子も男の子だったと発表した。ただし、帝国皇帝と聖ロドニウス教会総院長とには真実を告げて―――その真実がどこまでのものかはラインハルトには知る由もないが・・・ それにしても、ルドルフに聖少女の資格があるということは、彼女にはこの世を変えてしまうくらいの大きな力を操ることができるかもしれない、ということだ。 あの、オーブで飛んだ不思議な空間で見たルドルフの姿は確かにどこか異質で異様な感じがした。 ラインハルトの脳裏にふいにエドマンド前総院長の遺した言葉が蘇った。 ―――闇に閉ざされた空に赤い月が昇る。あれはこの世に生まれ出るべきではなかった。だが運命の輪には逆らえない。変革の時は近い。大地は燃え、人間が覇者であった時代は終わる――― あれはこの世に生まれ出るべきではなかった・・・ 『あれ』とはまさか、聖少女であるルドルフのことではないか? ラインハルトは一瞬絶句し、すぐにそんな考えを頭から吹き飛ばした。 ほんの一瞬でも友のことをそんな風に考えた自分が恥ずかしい、と思った。 ルドルフがそんな忌まわしいものであるはずがない。もしそうなる資質が生まれながらにあったとしても、彼女ならそんなものには絶対なるはずがないではないか! そうだ、あの日記のことを忘れていた。ルドルフは水に濡れると字が浮かび上がるとか言っていた。 できればルドルフと一緒に読みたかったが、先ほどのモレナ様の様子では当分彼女に会わせてはもらえない気がする。 ロナウドも眼を覚ましていないようだし、今のうちにざっとでも読んでおこうか・・・ 頭痛はまだ続いていたが、ラインハルトはどうにか身体をベッドから引きはがし、テーブルの上に置かれた水差しからほんの少しばかり手に水をすくうと、日記の白紙のページの上でその手をさっと翻した。 ラインハルトの手から零れおちた水は細かい霧状になって日記を包みこむ。 ほどなく白紙と思われたページに流麗な筆記体が浮かび上がってきた。 日記には英雄ルドルフのグリスガルド戦役の状況が思うように進まず、帝国から密使が遣わされたことが記されている。そのくだりの記述振りからルドルフ一世が当初その密使を快く思わなかったことが窺い知れた。 その密使は魔道士の一団で、彼らの放つ強烈な光の魔法により事態は一気にフィルデンラント側に有利に傾いていった。 魔道士群団の活躍でどうにかグリスデルガルド上陸を果たしたルドルフ一行だが、最後の牙城死守に燃える妖魔族の猛攻もすさまじいものがあったようだ。 火に焼かれた大地が闇を切り裂く光の魔法で浮かび上がり累々と積み重なる死体の山を浮かび上がらせる。 火で焼かれた兵士は復活することがないのを知って、戦に倒れた兵士の遺体は敵の手に渡る前に回収し火葬することが義務付けられた。 一方強い光にさらされた相手は断末魔とともに黒い霧となって霧散するが、中にはどす黒い血を流して倒れる者もいた。 いずれにしろ人が倒れ命の火が消えていくのを目の当たりにするのは、決して気持のいいものではない。 兄フランツ王子の即位のことがなければ、英雄の心はとうに崩折れていたのだろうと思われた。 グリスデルガルドに駐屯にしていく度目かの春を迎えようという時期――― 日記の記述が唐突に変わったのが分かる。 小さな島であるグリスデルガルドの攻略が一向に進まぬことに業を煮やした帝国からの矢のような催促に答えるために、英雄ルドルフは果敢な奇襲作戦を敢行する。 その成果あってフィルデンラント軍は小さな神殿の一つを占拠することができたらしい。 その神殿は敵が常駐するものではなく、何かの儀式の折にだけ使用されるもののようだが、仮のテント住まいの長かった兵士たちにとって、屋根のある休息所はこの上なくありがたいものだった。 敵が取り返しに来ることは自明の理だったが、フィルデンラント軍としても前線基地としてこの神殿は何としても守り抜く気概にあふれていた。 戦局が一進一退を続ける中、ある夜、ルドルフは不思議な光景を目にする。 兵舎の周りのあちこちに鬼火が現れては消えた。 どうも相手の奇襲攻撃ではないらしい。 不思議なことにこの数日敵からの攻撃は止まっていたのだ。 ただし、こちらを油断させてのおとり作戦ということも十分考えられる。 ルドルフは一方向だけ鬼火が発生していないのに気づき、鬼火の対応に追われる他の兵士たちには告げずに単身その方向へと忍んで行った。 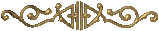 ―――背の高さほどもある雑草の茂みを音をたてないように気配を忍ばせながらどれほど歩いたことか、ふいに草叢の間から開けた景色が目に飛び込んできた。 そこは一面の花畑。名を知らぬ大そう美しい花が一面に群れて咲いている。 百合に似ているようだが百合ではない。月の光を浴びた花々は互いに競い合うように銀色の光を放ち、むせるような香気を放っていた。 無数の鬼火や羽根の生えた妖精たちが宙を舞うその中心には、あきれるほどに冴え冴えと輝く月光を浴びて一人の女性がうずくまっていた。 不意に子供の声がする。 「姉様、守備はどう?」 「ありがとう、おかげで月光草をこんなにたくさん摘むことができたわ。ミュゼルーシアのお祭りにはやっぱり月光草を供えなくてはね」 そう答えるのは鈴を転がすように高く美しい若い女性の声だった。 立ち上がった女性の腕にはかの花束が溢れるほどに抱えられている。 そのすぐ傍らにいつの間に姿を現したのか、黒ずくめの少年が立っていた。 花の匂いがきつすぎるのか、妖精たちのせいか二人は私の気配には気付かないらしい。 「花摘みが終わったなら早く戻ろう。誰かが目くらましを見破らないとも限らないから・・・」 「まあ、マティアスにしては珍しく慎重なこと」 「敵軍にもいやな魔道士が結構いるからね」 「あなたに敵う者などいないでしょうに」 「レティ!」 「待って、マティアス、もう少しだけ月の光を浴びていたいわ・・・」 かの女性の瞳が月の光を受けて七色に移ろうのを目にし、私は思わず草叢を掻き分け彼らの前に姿を曝していた。 黒い髪の姉弟―――この二人は間違いなく妖魔族―――敵だ! だが、レティと呼ばれたかの人の瞳はただただ静謐を湛え、そこに敵意は感じられなかった。 遠目で想像していたよりもはるかに美しい・・・ 「あなたはどなたなの?どうしてここへ?」 「レティ、こいつは・・・」 四つの眼が私を見つめている。いずれも光を受けて色を変える不思議な瞳だ。 私はとっさに答えた。 「私はフィルデンラントの名もなき一兵士。月の光に導かれるままにここへたどり着きました」 二人は一瞬絶句する。だがすぐに少年の方が口を開いた。 「嘘を吐くな。我らにはすぐわかる。その腰に差した剣はもともとは我ら一族に属する宝剣。そんなものを一兵士が持ち歩けるはずがあろうか」 「この剣が貴方方の・・・」 女性は静かに頷く。 この瞳を前に嘘はつけない―――私は真実を告げることにした。 「失礼しました。私はルドルフ・オレステス・フォン・フィルドクリフト。フィルデンラント第二王子にしてグリスデルガルド侵攻軍の総帥です。ただ、月の光に導かれでこの場所に来たのは嘘ではありません」 「あなたがルドルフ王子なら私たちを殺しますか?」 彼女は幼い弟を後ろ手に庇いながら静かに私を見つめている。 「私は・・・。あなたを敵と思うことはできそうもない。どうかこのまま立ち去ってください。あなた方に会ったことは忘れるとしよう」 「レティ、こんなやつ僕が・・・」 子供は私に手を伸ばそうとするが彼女はそれを優しく押しとどめた。 「ありがとう、私はレティシア・デ・トレイヴァス、弟はマティアスといいます」 「レティシア。綺麗な名だ。貴女に相応しい」 「気安く呼ぶな!セレスティン公爵令嬢だぞ」 その言葉にレティシアの口元にはわずかな微笑が浮かんだ。 「貴方に神のご加護がありますように」 二人は身をひるがえして消え去ろうとする。その後ろ姿に私は呼びかけた。 「あなた方の神のご加護ですか?」 少しばかり揶揄を込めた私の言葉に彼女は 「私は神に仕える巫女ですから」 と微笑を浮かべて答えたのだった――― 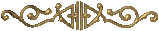 日記の文章はラインハルトに衝撃を与えた。 レティシアとマティアスだって!! マティアスって、まさか、あの皇帝セドリックと一緒にいた奴か! そういえばレティシアという名にも聞き覚えがあった。 そう、あのセドリックが言っていた言葉――― 『なぜお前は生きているのだ、レティシアは死んだというのに・・・』 いや、そんなはずはない、この日記が書かれたのは何百年も前のはずだ。 同じ名前の別人に決まっている。代々兄弟姉妹で同じ名を受け継ぐことはよくあることだ。フィルドクリフト家のフランツとルドルフのように。 いくら妖魔族が長命といってもそんなに長く生きられるはずがない。 だが、あの間欠泉に現れた妖魔族の男は言っていた、エリオルは何年たっても少しも年を取らず・・・ 酷い頭痛にラインハルトは頭を抱え込んだ。 その後神殿を中継基地としたフィルデンラント軍は、魔道士軍団の活躍もあり制圧地域を徐々にではあるが確実に広げていく。 しかし、ルドルフ一世の日記では戦況の記述は以前と比べてかなりお座なりなものとなっているのが感じられた。 英雄の中に、この戦いの必然性への疑問が湧きあがってきたのだ。 白の帝国と聖ロドニウス教会に命じられるままグリスデルガルドに侵攻し、制圧すること、そして逆らう者は神の軍隊に刃向う反逆者として容赦なく撃滅すること―――それが真に正しいことなのかどうか。 ルドルフ一世がそんなことを考えるようになった原因は明白だ。 レティシア―――彼女との出会いが、兄のことしか頭にない武骨な軍人だった男を変えた。 さすがに色恋に疎いラインハルトでもすぐに分かった、ルドルフ一世がレティシアと名乗った女性に一目で恋に落ちたことが。 |
 ゾーネンニーデルン ロディウムの隠れ里 モレナの話を信じるとすれば、瀕死のルドルフ一世を救った妖魔族の娘というのがこのレティシアであることはほぼ間違いなかろう。 この先二人に一体何が起こってそういうことになったものか・・・ 頭痛はますます酷くなり、頭をハンマーで殴られているようだ。だが、今はこの日記を読み終えてしまわなくてはいけない気がして、ラインハルトはページを繰り続けた。 しばらくはまた同じような記述が続くが、日記を書く頻度は初期に比べて明らかに少なくなっている。時には半年くらい記述が飛んでいるときもあった。 特に書くようなこともなくなってきたというわけなのだろうか。 やがてグリスデルガルド全域の制圧まであとわずかと思われるところで、次のような記述にラインハルトの眼が止まった。 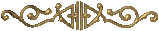 ―――今日故国より久々の急使が届いた。それは父の逝去と兄の皇位継承を伝えるものだった。 いまだ帝国との交換条件であるグリスデルガルド攻略はなっていないが、なおも兄の廃嫡を画策する父の突然の死により、兄が王位を継ぐことに反対する者はほとんどいなかったとのこと。 父がいなくなれば、帝国と聖ロドニウス教会を後ろ盾にもつ兄に正面切って逆らおうとするものはいないはず。 少なくともそうなりそうな危惧のある勢力はことごとく根絶やしになっているはずだ。フェルクトマイヤーよりの報告に嘘がなければ・・・ それにしてもフェルクトマイヤーには感謝しなければなるまい。 今回の父の死の裏にもおそらく彼の手が回っていることだろう。 その代償としてあの男がどれほどの報酬を要求してくるか気がかりであるが。 急使は兄の戴冠にあたり、この私に一時帰国を促す兄からの親書をも携えていた。 ただ一人真に兄弟と呼べるのは私のみ。その私に是非戴冠を寿いでもらいたいというのが兄の願いだ。 戦役のため故国を離れてどれだけの日が過ぎたのか、もう数えるのも億劫になってしまうほどの時間が流れたような気がする。 兄の戴冠の姿を見るのは私の長年の夢だった。何をさしおいても帰国して栄えある式典に出席したい。 だが、私はまだこの戦役の本来の目的を果たせないままだ。 故国を離れる際、その目的を果たすまで故国の地は踏まぬと神に誓いを立てた。 その誓いを破ることはできない。 今の私にその任を果たせる自信はほとんどないが・・・ 兄には今戦場を後にして自分一人帰国することはできない旨書き送るしかなかった。 無念だ――― 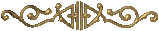 フェルクトマイヤーというのは日記の冒頭にも出てきた名だ。ルドルフ一世がリストを渡したとかいう・・・ その名がヴィクトールの姓名と同じことにラインハルトは暗澹たる気持ちになった。 ルドルフ一世が依頼したのは間違いなく兄を追い落とそうとする父の愛妾一派の粛清、さらには父王その人をも・・・ フェルクトマイヤー一族はこれを政界への進出の足掛かりとしたのだろう。 建国以来の旧貴族ではないフェルクトマイヤー一族が国王に次ぐ勢力を維持していることを、ラインハルトもかつて不思議に思ったことはあった。 彼を重用したということはフランツ王もルドルフ一世との密約を知っていたということなのだろう。 どうにも気分の悪い話ではある。 だがそれ以上にラインハルトの注意を引いたのは後半の一文――― ルドルフ一世がその目的を果たすまでは故国の土を踏まぬと立てた誓いのくだりだ。 日記の記述を信じるとすれば、グリスデルガルドの一応の制圧は目途が立ったように思われる。 にもかかわらずルドルフ一世がやけに気弱になっているのは、なぜだろうか。 レティシアの存在が英雄の心に影を落としているのか、あるいは・・・ この戦役の真の目的はグリスデルガルドの制圧とは別のところにあるのかもしれない。ラインハルトはふと、そう思った。 やがて捕虜にした妖魔族の男から貴重な情報がもたらされる。 妖魔族は光の魔法を浴びるとたいてい黒い霧となって消えうせてしまうが、中には黒い血を流して倒れるものもあった。 そういった者たちはほとんど舌を噛み切って自死を選ぶが、そのうちの一人の命をどうにか取りとめ、尋問することができたのだった。 男はなんと妖魔族と人間、両方の血を引いているという。 男から貴重な情報を得たルドルフ一世は戦局を一気に終結へと導くためある作戦を展開することにしたらしい。 ルドルフ一世が終戦を急いだのには理由があった。 故国から再び急使が届いたのだ。 それは新国王フランツの病を告げるものだった。病は重篤で、万が一の場合に備えてルドルフ王子の帰国を促すものだった。 フランツには世継の王子がいたがまだ幼少だ。 この機に乗じて亡き父を未だに信奉する者たちがおかしな動きを始めないとも限らない。 それ以上に・・・もう二度と兄の顔を見れないかもしれない、と思うとルドルフ一世の心は揺れた。 今度ばかりはルドルフも帰国を急がざるを得ず、戦局を一気に終結へと向かわせるための作戦に打って出たのだった。 その作戦については軍事機密のせいか日記にも詳しく書かれてはいなかった。 ただ、作戦成功の暁にはルドルフ一世としては妖魔族と休戦協定を結ぶつもりだったらしい。 ある条件の下妖魔族の存続を認めるかわりにグリスデルガルドの地はフィルデンラントの領土とする主旨の。 そして数ページの記述ののち唐突に日記は終わっていた。 まともな記述は作戦実行の前日まで。 次ページには見開きいっぱいを大きく黒い染みが占め、下端にただ一言『絶望』と殴り書きがされていた。 さらに次の見開きには、私は故国フィルデンラントへ帰還を果たした、と記され、あとはすべて白紙のままだった。 さらに記述が隠されているのかとも思いいろいろやってみたが、本当に初めから何も書かれていないらしい。 結局どんな作戦が敢行され、その結果がどうなったのかは分からずじまいだった。 その後の歴史と現状を考えるとこの作戦は成功し、それにより妖魔族と何らかの協定を結ぶことができたルドルフ一世は帰国の途につけたのだろう。 ただそうなると、ルドルフ一世が、それを果たすまでは故国の土を踏まぬ、という誓いを立てたというこの征西の本来の目的とは何だったのだろうか、とラインハルトは思った。 |
 ゾーネンニーデルン ロディウムの隠れ里 肝心なことは曖昧なまま、人の心の中を覗き見したような後味の悪さだけが残る。 「結局よくわからないままか」 ラインハルトは日記を乱雑にテーブルに投げ出すと、再びベッドに身を沈めた。 大きく溜息をつき目を閉じてみたが眠れそうにない。 それでも疲れた頭と体を少しでも休ませようと眠る努力はしてみたのだが・・・ 暫く呻吟したあと、とうとう眠るのを諦めたラインハルトは外の空気が吸いたくなって、まだ頭痛の残る頭に手を当てながら静かに部屋を出た。 ロナウドはまだ目覚めないのかな、そう呟きながら石造りの廊下をたどると、中庭を巡る回廊に出た。 外はいつの間にか夕闇がおりている。 思いのほか長いことモレナの部屋にいたのか、あるいは自分でも気付かぬうちに少しは眠っていたものか。 さまざまな草花が咲き乱れる中庭の中心には噴水があって、清らかな水が溢れ出していた。 ラインハルトは噴水の縁石に腰掛けふうっと溜息をついた。 ここはなんて清々しい場所なんだろう。この水は地下水路で他の噴水ともつながっているのだろうか。 そっと水面を覗きこみ清冽そうな水に手を浸してみた。 すると――― 不思議な光景が水面に映って見えた。 あれ、これは・・・ どこか鄙びた草原を満月が煌々と照らしている。その中に一人たたずむ若い女性。 その足許には百合に似た光り輝く花が咲き乱れている。そして女性の腕の中にもその花束が抱かれていた。 月の光を浴びて七色に変わる瞳。 女性の周りをたくさんの花の精が乱舞している。 綺麗な女性だ。どこかルドルフに似ていると思うのは同じ黒髪だからだろうか・・・ その姿を見つめているとひどい頭痛がいつの間にか治まって、気分が落ち着いてくるのが自分でも分かった。 安らぎ、憩い、そういったものをその女性は体現しているような気がする。 これがレティシアという女性なのだろう、とラインハルトは直感した。 不思議な里の不思議な力の宿る水が、自分の持つ力と反応して過去の一事象を眼前にあるがごとくに映し出したのだろう。 それならば、兄ヴィンフリートがどうなったのかも映し出してはくれないだろうか。 ラインハルトが兄に思いを馳せた瞬間、場の空気が変わり、安らぎの空間ははじけ飛んだ。 「まあ、お前私の従者ではないわね。こんなところにいるから、てっきり」 いつの間に現れたのか栗色の髪の少女が回廊の端からこちらを見つめていた。 虚を突かれたラインハルトはただポカンと相手を見つめたまま言葉もない。 「そんなに、呆けたような顔をしなくてもよいでしょうに。どうやら里のものでもないようだし、お前はだあれ?」 我に返ったラインハルトは憮然として答える。 「人に名を訊ねるなら自分から名乗るのが礼儀だろう。君こそ誰なんだ。何故、僕の邪魔をする」 「まあ、どうやら聖ロドニウス教会の学僧のようだけど、少し横柄過ぎるのではなくて。私は・・・」 ラインハルトは自分がまだ僧侶の格好をしていたことを思い出し確かに少し横柄だったかもしれない、と思った。 だが、貴重な思索の時間を邪魔されたという思いは強い。 先ほどまでの清浄な雰囲気は一気に霧散してしまっていた。 もう兄の姿を追うことは難しいだろう。 ラインハルトの落胆ぶりを目の当たりにして、少女は少し気まずそうに言葉を継いだ。 「もう、確かにいきなり邪魔をしたのは悪かったわ。私はサンドラ。従者とともに旅をしてきたの。昨日までは快適な旅だったのに、連れとははぐれるし、火山の噴火には巻き込まれるし、もっと最悪なことに長年信頼してきた侍女が裏切り者であることが分かったのよ。でもどうすることもできなくて・・・・・・」 「サンドラ・・・?」 ラインハルトは改めて少女の様子を見やった。 物腰や服装から相当高い身分であることは間違いないようだ。 ラインハルトは不意にルドルフから聞いた名前を思い出す。 「そうか、サンドラって確かゾーネンニーデルンの庶出の王女がそんな名前だったっけ・・・」 ラインハルトは小声で呟いたつもりだったが、相手にはしっかりと届いてしまったようだ。 「庶出の、だけ余計よ。好きでここに来たわけではないし。 だいたいこんな山の中にこんな集落があるなんて思ってもみなかったし。貴方はどうしてここへ来たの?ここは僧侶の修行の場か何かなの?」 「いや、僕は、その」 ジネヴラの言っていた厄介なお客人とはこの少女のことか――― 返答に窮するラインハルトを見て、サンドラは気を取り直したように、 「私ったらなんで初対面の名前も名乗らないような相手にこんなこと話してるのかしら・・・」 といって照れたように笑った。 その笑顔にラインハルトの心も少し軽くなる。 笑顔にはそういう効用があるのだ、とラインハルトは改めて思う。 「さきほどは失礼、僕はラインハルト、わけあってこの里に身を寄せています。僧侶として貴女のお話をゆっくり聞いてあげられる余裕があればいいのですが」 とっさに偽名を使おうかとも思ったが、この清浄な場所で嘘を吐くのは後味が悪そうだ。 「ラインハルト・・・貴方もしかして」 少女はラインハルトの顔をじっと見つめている。 自分も本当の身分を明かすべきか咄嗟に判断がつかず、戸惑っていたラインハルトに救いの手を差し伸べてくれたのはジネヴラだった。 反対側の回廊から音もなく姿を現したジネヴラは、 「ラインハルト様、お連れの少年が目を覚ましました。お会いになりますか?」 と声をかけた。 「あ、はい、できれば」 ジネヴラはラインハルトに軽く手招きすると、サンドラには、 「貴女様にはご寝所からお出にならないようにと固くお願いしたはず。なぜこのような場所にいらっしゃるのです」 言葉づかいは丁寧だがその口調には強い非難が込められている。 「私は誰の命令も受けない。私は自分の行きたい所に行くわ」 「命令ではなくお願いしたつもりですが」 「同じことじゃないの。その人は自由に出歩けるのだから私にも同じように・・・」 サンドラの声は少しずつ弱まり、その瞳の輝きも薄れていく。 「わかったわ。部屋に戻ることにするわ」 そう言ってラインハルトには一瞥もくれずふいに身体を翻すと、サンドラは静かに元来た方へと去って行った。 ジネヴラには相手の意志を思いのままに操る力があるようだ。 ラインハルトは軽い溜息とともに彼女の後に続き、ロナウドの部屋へと向かった。 |
 ゾーネンニーデルン ロディウムの隠れ里 「ラインハルトの部屋とよく似た作りのこぎれいな部屋にロナウドは寝かされていて、そばには年配の女性が付き添っている。 ジネヴラに続きラインハルトが部屋に入るとロナウドは慌てて起き上がろうとしてその女性に止められた。 「まだ起き上がってはいけませんよ。足の捻挫は治りきっていないのですから」 「でも、ラインハルト様が」 「僕のことは気にしなくていいよ、ロナウド。気分はどう?」 「はい、少し頭が痛いですが、大丈夫です。それより僕はどうしてこんなとこにいるのですか? 確か暴漢に襲われて・・・ラインハルト様が助けてくださったのですか?」 「いや、君はその連中に拉致されてここへ連れてこられたようだ。そして、この里の方々が君を保護してくれたんだ」 ラインハルトはそういうとジネヴラをロナウドに視線で示した。 ロナウドは無言でジネヴラに会釈し謝意を示す。 「足を怪我したの?大丈夫かい」 ラインハルトはベッドに近寄り、付添いの女性の傍に立って訊ねた。 「はい、僕薬草を摘もうとしていたら、急に目の前に飛び出してきた人達がいて、その人たちが剣を振り回しているのを見て、慌てて逃げ出そうとして足を滑らせてしまって・・・」 「その時に足を捻挫したようですね」 ジネヴラが優しく言葉をはさむ。 「ラインハルト様、申し訳ありません。僕は転んだはずみにオーブをとり落としてしまって、その連中に取り上げられてしまいました。それを取り返そうとしたのですが、どうやら気絶させられてしまったようです」 「やっぱりそうか」 里に入ったところで声をかけてきた連中が、それだろう。キナ臭いという形容詞がぴったりの男たちだった。 ラインハルトの顔が一瞬曇ったが、それを見てすぐにジネヴラが言葉を挟んだ。 「ご安心いただいて大丈夫ですよ、ラインハルト様。あの者たちが貴方のお連れから奪った物は、私がお預かりしておりますから。あの者たちを里に迎える条件として長に献上させました。 勿論私達はあれがどのような経緯であの者たちの手に渡ったものか察しはついておりましたから、これは正当な持ち主に返却するといいおいてあります」 「正当な持ち主」 本来ならそれは聖ロドニウス教会であるはずだが・・・ 「つい先ごろまでは聖ロドニウス教会にあったものが不思議なめぐり合わせでこの里へたどり着いた。おそらくこれも偶然ではないのでしょう。石はそれぞれに引きあう性質がありますから」 ロナウドに配慮してかジネヴラはただ「石」とだけ言ったが、その意味するところが聖石であるところはすぐに分かった。 そう、いままで聖地の奥深くに隠されていた石が外の世界に現れることになった。他の石まで呼び寄せながら――― ジネヴラの言う正当な持ち主が聖ロドニウス教会ではなくルドルフを指していることは明白だった。 「ジネヴラ様、ロナウドを保護してくださってありがとうございました。無事な様子を見てホッとしています。ところでルドルフはどうしていますか。まだ休養中でしょうか? 僕は彼女と話さなくてはならないことができてしまいました」 ラインハルトがルドルフのことを『彼女』と呼ぶのを聞いてロナウドは少し不思議そうな顔をしたが、ラインハルトはそれには気付かなかった。 「ルドルフ様はまだお眠りになっていらっしゃるようです。だいぶお疲れのようでしたから。もう少し休ませてあげた方がよろしいでしょう。その間ラインハルト様もお食事をお取りくださいな。このような山里で大したおもてなしもできませんが、ゆっくりくつろいでくださいませ。ルドルフ様が目を覚まされたら、またお知らせいたしますので」 ロナウドにも今しばらく休息が必要ということで、ラインハルトはジネヴラに案内されるまま食堂へと向かった。 |
 ゾーネンニーデルン ロディウムの隠れ里 広めの食堂には先客がいて、給仕の女性になにやら声高に命令しているのが部屋の外からも聞こえてきた。 先ほどの少女サンドラであることは明白だ。 彼女と同席とは少々気が重いが客分である以上文句も言えまい。 サンドラは何やらさかんにまくしたてていたが、ジネヴラの姿を入口に認めるとふいに口をつぐんだ。 「お客人、お料理にご不満はおありでしょうが、ここは宮殿のようなわけにはまいりませんので、ご容赦願います」 「分かっています。もういいわ」 サンドラは大人しく従ったが今度はジネヴラと目を合わせようとはしない。 ジネヴラの力に気付いてのことだとしたら、見かけ以上に聡い子かもしれない、とラインハルトは思った。 ジネヴラは、「お二人は顔見知りでしたね。では紹介無用ということで」と言い置くとラインハルトを残して出て行ってしまう。 仕方なく、 「ご同席願ってもよろしいでしょうか、王女様」 と声をかけながら、返事を待たずに腰を下ろした。 「いやだと言っても無駄でしょうに」 そんな呟きは聞こえなかったこととして無視し、給仕される食事を楽しむことにする。 何といってもフォン・カステルの離宮を離れて以来久々のまともな食事だ。 聖ロドニウス教会ではいくら気を使ってくれてはいても、本来が修道僧の食事ということでかなり質素なものだった。 ジネヴラは謙遜していたが、コックの腕はなかなか大したものでラインハルトも十分に堪能できるものだった。 初めサンドラは無言で、わざと乱暴にちぎったパンを思いっきり頬ばったりしでいたが、やがて沈黙に耐えられなくなったようで、不意にラインハルトに話しかけてきた。 「貴方はゾーネンニーデルンは初めて?」 「え、どうして?」 「だって貴方はよその国の人でしょう。ここは南国、貴方みたいにきれいな金髪の人はまずいないわ。それに貴方の話し方は少しだけど北方系のアクセントが強い。たぶんノルドファフスベルクほで北ではないでしょうから、フィルデンラント北部出身、どう?違っていて?」 「ええ、そう、その通りだ。僕はフィルデンラントの出身です」 暫く沈黙ののち一足先に食事を終えたサンドラがナプキンで口をぬぐいながらさらに訊ねてきた。 「そう、それでこの国のどことどこへ行ったの?」 「どこって、僕はこの国に着いたばかりで」 「そうなの? では本当はどこへ行くつもりだったの? こんなところへ来てしまったのは本意ではなかったのでしょう?」 「どうしてそんなことを?」 「だって、貴方は本当は僧侶ではないでしょう。そんな格好をしているだけで。食事の様子とか見ればすぐに分かるわ」 「そうだね、僧侶はこういう食事は遠慮するだろうね」 ラインハルトはジネヴラがロナウドと食事を分けた理由がやっと分かった。 「もう少し気を配らないと変装は成功しないわよ」 「ああ、そうなんだけど、もうそんな余裕なくて・・・。僕は友人に借りた物を返したかっただけなんだけど」 食欲が満たされほっとしたのと自分の不用意さが情けなくなったのが重なって、ラインハルトの瞳には不意に涙がこみ上げてきたが、サンドラの面前ということでどうにか堪えた。 「友人がゾーネンニーデルンにいるの? 借り物はもう返せたのかしら?」 「まあなんとかね。でもこれからどうしたらよいのか、僕にはよく分からなくなってしまった・・・あ、いや」 サンドラにあまりにもじっと見つめられてラインハルトは照れ笑いをした。 「何を言ってるんだろうな、僕は。ところで君はどうしてここへ?従者がどうとか言っていたけど」 「私は・・・あちこち旅をしていたのよ。宮廷にいても退屈だし。ずいぶんいろいろな所にいったわ。この国を出ることはできないけどね」 「ふうん」 食事を続けるラインハルトを前にデザートを頬張りながらサンドラは話し始めた。 孤独な宮廷での生活のこと、旅の途中で見聞きした珍しい話。ルドルフという連れと出会ったこと、またロディウムの温泉の話――― 話し出すと歯止めが利かなくなって、休む間もなく話し続ける。 なんだか話し続けていないと不安でたまらないという感じだ。 女性のお喋りに付き合うのに慣れていないラインハルトはとうとう話の継ぎ目をみつけて訊ねてみた。 「王女様としてはやけに僕を信頼してくださっているみたいだけど、初めて会った相手にそんなに何でも話していいの?」 サンドラは虚を突かれたように一瞬ポカンとラインハルトを見つめたが 「何言ってるの。貴方はフィルデンラントのラインハルト王子でしょう。噂ではグリスデルガルドの政変に巻き込まれて亡くなったことになっているけど」 と事もなげに言った。 今度はラインハルトがぎょっとして相手を見つめる。 「いまさら何を驚くことがあって?私は一目でわかったわよ。フィルデンラントの王族は日に輝く金の髪に薄水色の瞳―――誰でも知ってる話よ。 フィルデンラントのラインハルト王子はグリスデルガルドの政変で命を落とした。フィルデンラントはその報復としてグリスデルガルドに侵攻する。その最中に病弱だった国王は逝去。跡目はどうやら相当傍系の王族に回っていくらしい――― っていうのが巷の噂だけど、いかにも胡散臭い筋立てよね。裏があるだろうって私にだって分かるもの」 見かけ以上に聡明だと感じたのはやはり間違いではなかった。 「君は―――」 「貴方は私の身分を知って名前を偽ることもできたのにそうしなかった。だから信頼できる相手だと思ったわ」 「それは・・・どうも」 「小さい頃から見なくてもいいことばかり見てきたから、私、余計な事に気が回るみたいなの。 でも、こんなこと話したのは貴方が初めて、いえ、二人目だわね。一人はとんでもない裏切りものだった。そんなことはどうでもいいわ、私だって自分の身は護りたいもの、傍目にはわがままで少し足りないくらいの王女様を演じていた方が都合がよかったのよ。 でもこれは内緒。貴方だから話したのだから。 で、裏で手を引いているのは敏腕宰相と名高いフェルクトマイヤー卿あたりかしら?」 「まあ、そんなとこだ。それと・・・妖魔族」 「!」 サンドラは大きく目を見開いたが、やがて少し上目遣いでラインハルトを見つめながら訊ねた。 「ねえ・・・、庶出とはいえゾーネンニーデルンの王女が今ここでフィルデンラントの王子に出会ったというのは単なる偶然なのかしら」 ラインハルトはしばし躊躇したのち、言葉を選びながら慎重に話を進めた。 「僕にはよく分からない。君もさっき言っていたけど、フィルデンラントでは兄国王の逝去が正式に発表され、傍系の血筋から新国王を立てようという陰謀が画策されている。僕は死んだことになってしまっているし、聖ロドニウス教会も今となっては信頼できない。正直ゾーネンニーデルンのヘンドリック王子に助力を請えれば、と思っていた。でも・・・」 「でも?」 「君に言っていいかどうかよくわからないが、君の一行を襲ったのはゾーネンニーデルンの正規兵だろう、とすればその命令を下したのは・・・」 「分かってる。私のことをつけ狙っていたのは兄のヘンドリックよ。私には政治的な野心などない。けど、猜疑心の強い兄はそうは思っていない。 私はつまらない政争に巻き込まれたくなくて宮廷から離れるようにしていたけど、兄はそれを変に邪推しているのかもしれないわ。 それでも今までは命まで狙ってはこなかったけど、今回の襲撃は違った。兄ははっきり私を暗殺しようとしてきたのよ。兄の周辺で何か変化があったのだと思うわ」 「ヘンドリック王子には何年か前に一度フィルデンラントでお会いしたことがあるけど、聡明で公平な王子だという印象だったが」 「ええ、少し前まではその通りの王子だったわ。私の自慢の兄だったのよ。それなのに二年くらい前からおかしくなったの。兄が私の命を狙うなんて・・・本当は信じたくないのだけれど。 それに子供の頃から仕えてくれた次女のアリサが私を裏切って兄と通じていたなんて」 「ヘンドリック王子がおかしくなったのは二年くらい前から?」 「ええ、そうよ。今まで傍で仕えてくれた者を皆遠ざけてしまって、得体のしれない人たちを周りに侍らせて、重要なことも父に相談なしに勝手に決めてしまうようになって。 それで最近では父も本気で兄の王位継承を考え直し始めたようなの。それが今回の襲撃と結びついているのだと私は思っているわ」 ヘンドリック王子の周辺にも妖魔族の手が伸びているのか・・・? 「でも、ヘンドリック王子の王位継承問題と君の襲撃とどう結びつくのかわからないな。ゾーネンニーデルンには正妃腹の王女がいるだろうに。君は・・・」 「その言い方本当に失礼よね、まあ真実ではあるけど。確かに義姉が二人いるけど、一人は修道院に入ることが決まっているし、もう一人は・・・」 「どうしたの?」 「私の口から言いたくはないけど、もう一人のお姉さまはお父様の子供ではないというのが公然の秘密なのよ。ご本人は何も知らないようだけれど。 父としてはもし兄に何かあった時は後を継がせるのは私だと、この間帰国したときこっそり言われたわ」 サンドラとしてはその義姉と貴方との間に縁談があったのよ、と言ってみたい気持ちに駆られたが、ラインハルトがそういう話を喜びそうもないことは何となく分かっていたので心の中で呟くだけにしておいた。 本来の血筋がどうあろうとも、義姉がゾーネンニーデルンの正妃腹の王女であることは否定できない。本当は自分の方が血統では上だと思うのに、日陰の身として一歩控えていなければならないことが、サンドラにとっては長年の不満の種だった。 本当はこんなこと他国の王族に話してはいけないことなのだろうが、今のサンドラは胸に詰まった全てを誰かに吐き出してしまわずにはいられず、また口からあふれ出た言葉がとめどなく流れ出るのを抑えることができなかった。 「ゾーネンニーデルンの宮廷でもおかしな動きが・・・。何だかできすぎている感じがする」 「え?」 「おかしいのはフィルデンラントやゾーネンニーデルンだけではないかもしれないね。実際聖ロドニウス教会でも上層部は一枚岩ではないようだったし」 「そうね・・・最近いやな噂を聞いたわ。北東の国アイゲンシュタインで軍備増強が進められていて、その狙いはどうやら隣国ゲルトマイシュタルフの併合らしいって」 「アイゲンシタイン!」 「そう、あそこも現国王が病気で第一王子が摂政よね。嫌な感じだわ」 給仕がラインハルトの食事を下げ、代わりにデザートを運んできた。 上質の果実のゼリーだが少しも味を感じない。 給仕の間だけ会話が途切れ、ラインハルトは溜息をつくのさえ忘れていたことに気が付いた。 その瞬間ラインハルトの脳裏にある映像がフラッシュのように浮かんでは消えた。 見渡す限りの草原を風に乗った火が覆いつくしていく。 草原の向こうに立ち並ぶ町並みも火に包まれていた。 思わず手にしたスプーンを取り落とすラインハルト。 だが、サンドラの次の言葉はさらにラインハルトを驚かせた。 「もしかして、今貴方にも見えたの?」 |